 当社で取り扱っている各種ボード製品に関連する技術情報ライブラリです。
当社で取り扱っている各種ボード製品に関連する技術情報ライブラリです。
カテゴリを選択すると関連する技術情報が表示されます。製品ページで不明な用語や規格の概要などをご確認いただけます。また、テックジャーナル(年1回発行)も併せてご確認ください。▶ テックジャーナル
高速インタフェース
高速インタフェース規格について解説
FPDP II

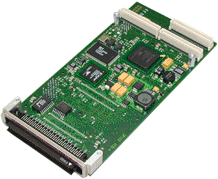
-
▮ ANSI/VITA 17 で標準規格化されている32bit パラレルの高速インタフェース
▮ 50MHz ダブルエッジのクロックで最大400MB/sec の転送が可能
▮ 組み込みシステム内で使用するものとしては比較的長い(10feet=約3m) ケーブルで 160MB/s の転送を実現していた FPDP のより上位の規格で、転送速度を 400MB/s まで引き上げている
▮ リボンケーブルを使用しており、ロイヤリティフリーで構造もシンプルなため、幅広く利用されている
Serial FPDP


-
▮ ANSI/VITA 17.1 で標準規格化。FPDP のプロトコルを踏襲してシリアル化した高速光インタフェース
▮ 光ファイバーを使うことによって、10km 以上のデータ伝送に対応した規格
▮ FPDP 同様、低レイテンシでリアルタイムデータストリーミングに強い構造で、特にセンサ/プロセッサ間の通信に向いている
▮ Serial FPDP は FPDP/FPDP Ⅱがベースになっているので、FPDP/FPDPⅡシステムからのアップグレードも比較的容易
sFPDPラインナップ
RapidIO

-
▮ 米国Motorola 社と米国Mercury Systems 社が開発した技術をベースとしたシステム間の相互高速接続アーキテクチャ
▮ チップ間、ボード間の接続のために開発された、パケット・スイッチを利用したインタフェース
▮ 規格はパラレルインタフェースから始まったが、現在は LVDS の高速シリアル通信をベースとした Serial Rapid IO が主流
▮ 標準化グループ:RapidIO Trade Association
Aurora

-
▮ Xilinx 社のRocketIO を使用した、高速でシンプルなシリアル通信リンクレイヤー・プロトコル
▮ Xilinx社より無料で提供されている
▮ フレーム構成がシンプルなため、オーバーヘッドも低く、またデバイスのリソース使用量も抑えられている
▮ Xilinx FPGA間の高速通信に利用されている
LVDS

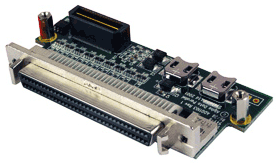
-
▮ TIA/EIA-644 で規格化された差動信号を使用した高速の信号伝送方式
▮ +/- の2本の信号を利用して電気信号を伝送する為ノイズの影響を受けない
▮ 信号線全体が近接している2本の信号の電位差で信号を伝送すると、同相ノイズ(コモンモードノイズ) の影響が打ち消される為、ノイズの影響を最小限にすることが可能
▮ 信号の電位差を可能な限り小さくすることで遷移時間を短縮し高速な通信を実現でき、消費電力も小さく押さえられる
▮ 現在の有線での高速通信は、ほとんどがこの技術をベースにしている
▮ 規格:TIA/EIA-644
LVDS I/Oボード
Fibre Channel


-
▮ 情報技術規格国際委員会(INCITS) のT11 技術委員会が標準化した、光ファイバを使用したギガビットのネットワーク技術
▮ 主にストレージネットワークで利用されているが、コンピュータ間の通信にも利用可能なギガビットクラスのインタフェース規格
▮ 現在 4Gbps まで利用されており、8Gbps 、10Gbps 以上の規格も検討中
▮ 標準化グループ: INCITS T11
Camera Link

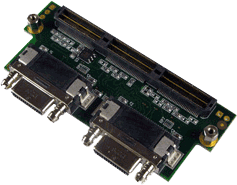
-
▮ 産業用カメラの画像伝送用インタフェースとして米国の自動化イメージング協会Automated Imaging Association によって規格化
▮ LVDS をベースとしたデジタルインタフェースで、画像データのほかに設定用のシリアル通信ライン、トリガとしても使える汎用コントロール信号 4bit を 28bit のコネクタに組み込むことで使い勝手が向上
▮ 伝送レートの要求により Base/Medium/Full の3種類のコンフィグレーションが規定されており、現在の技術では最高で 5.4Gbps ( フルHD で秒間 100 フレーム以上) の伝送が可能
▮ 標準化グループ:MachineVision
CameraLink FMC
10Gb Ethernet


-
▮ イーサネット技術を継承しつつギガビット・イーサネットの10倍の速度を提供する技術
▮ 光ファイバーと銅線の2種類が規定されている
▮ 従来のRJ45を採用した10GBASE-Tで最大100mとされている
▮ 光ケーブルを採用した10GBASE-LRや10GBASE-ERでは10km以上の通信が可能
10GbEボード
FireFly


-
▮ Samtec社が開発した基板間の高速インターコネクト技術で、光ケーブルと銅線ケーブルタイプがある
▮ x4レーンまたはx12レーン構成で最大28Gbpsの転送レートを実現する
▮ ケーブルは銅の場合Eye Speed® twinaxケーブル、光の場合OM3マルチモードファイバーを使用する
▮ 非常にコンパクトなコネクタ設計となっており、基板上のFPGAからダイレクトに入出力するポートとして利用される
▮ -40℃~+85℃をサポートした温度拡張版もある
ODI


-
▮ Keysight, Conduant, Samtec, Guzikの4社が開発した超高速光インタフェース(Optical Data Interface)規格
▮ 現在はAXIeコンソーシアムとVITAの業界団体により承認され標準規格となっている
▮ 簡単なプラグケーブルを介して機器間を(電気的ではなく)光学的な通信で接続する
▮ 最大20 GB/s(160 Gbps)、ポート集約により最大80 GB/s(640 Gbps)の通信速度を実現する
▮ 物理レイヤにInterakenプロトコルを利用している
ODI製品
